
クリエイティブディレクターとして目的地を定め、仲間と一緒に行動を起こす
2023新卒採用が始まっています!そこで、ミクシィで働くデザイナーのショートインタビューを公開します。
今日はBIT VALLEY 2021に携わったシニアデザイナーのお話です。
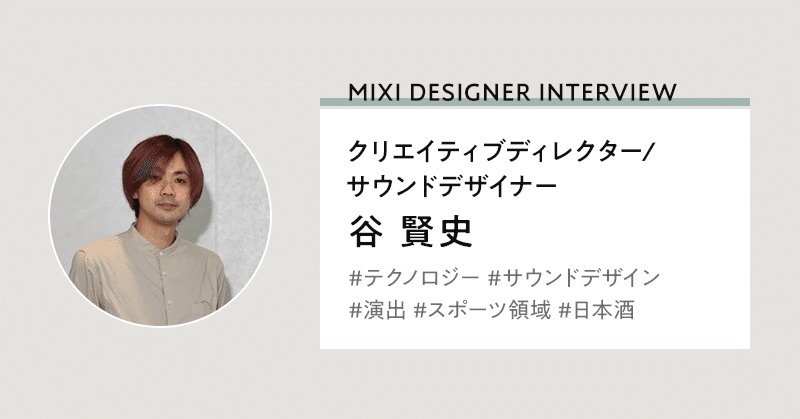
━━自己紹介をお願いします。
こんにちは、谷です。元々、音楽制作事務所に所属していて当時は音楽制作をはじめ、レコーディング、コンサート、楽器開発や音楽書籍など幅広く音楽に関わる現場にいました。その後は約15年ほどゲーム会社に所属し、サウンドデザイナーをしていました。
ミクシィではサウンドだけにとらわれずに、クリエイティブ全般に関わることが増え、今日お話しするBIT VALLEY 2021では、クリエイティブディレクターを担当しました。
━━そもそも、ミクシィに入社した経緯は。
ゲームで使われていた技術やノウハウは、今後リアルイベント、動画配信、スポーツなどの幅広い領域で使われていくことになるだろうと確信していて、ゲーム以外の分野にもチャレンジするために転職を考えました。
自身のキャリアとしても、ミクシィ入社直前、テーマパークのアトラクションを作っていました。その時もゲームで使われている技術やノウハウを活用して作り上げていきました。
自分のスキルをより幅広い領域で活かしていけるんじゃないかと思って、ミクシィに入社しました。
━━BIT VALLEY 2021のクリエイティブディレクターを担当したきっかけは?
デザイン本部長と1on1で話してる流れで「やりませんか?」と。その期待に応えたいなっていう思いと、自身も関わる領域を広げたかったので、苦労することにはなるだろうと自覚しつつも、チャレンジしてみようと。
━━会社としても、新しいチャレンジを応援する文化がありますよね。
自分のチャレンジしたいところに身を置くことができる制度もあるので、自らキャリアを切り開いたり、どういうことをしていきたいかみたいなことを相談しやすい雰囲気はあります。
今回のように声をかけてもらって挑戦してみるっていうのもありますし、興味ある人いますか?と聞かれて手を上げたりということも。そういうのはミクシィの社風でもあるのかなと感じますね。
━━さて、まずどんなことから着手しましたか?
「そもそもクリエイティブディレクターとはなにか」と、考えるところからスタートしたっていうのが正直なところで。
サウンドに関しては、ディレクターとして仕事をしてきたんですけど、それ以外の領域となると、やっぱり知識とかスキルとか全然知らないことも多いので。
なので、まずはクリエイティブディレクターはどういうことをやる必要があるのか、更に言うと今回の案件や、自分たちのデザイン組織を鑑みてどういう役割を担うべきかというところから考えました。
━━クリエイティブチームのメンバーは?
キービジュアルや各種グラフィックを手がけるグラフィックデザイナー。ウェブサイトの制作に携わるデザイナー、ディレクター、フロントエンドエンジニア。コンセプトムービー、イベント配信中のオープニング映像やアタック映像を制作する映像クリエイター。イベント配信の担当者といった、デザイン本部のメンバーに声をかけてクリエイティブチームを編成しました。
これとは別に、イベント全体を取り仕切る開発本部のDevRel(ディベロッパーリレーショングループ)とも連携していました。
━━社内資料に書いてあった『いつものやり方+1』とは...?
クリエイティブチームのメンバーは、すでに案件を数多く担当している経験豊かな人たちです。なので、いつもの自分たちのやり方は活かしつつ、それにプラスで新しいチャレンジが出来る箇所があればやってみようというのを、チーム立ち上げのミーティングで話させてもらいました。
━━コンセプトムービーについてお話を聞かせてください。
「Work From Anywhere」っていう、変わりゆく働き方や新しい働き方が今年のBIT VALLEY 2021のテーマの一つにあります。また、その更に抽象化した言葉として「働き方の多様性」というものがあります。更に深堀りすると働き方の多様性を考えることは、生活スタイルの多様性を考えることでもあります。
いろんな働き方を模索する一年だったと思います。その中で会社も働く人も意識の変化があったように感じます。更に、対面でのコミュニケーションだけでなく、遠隔のコミュニケーションが増えた一年でした。そこでは様々なテクノロジーが活かされています。そういった「テクノロジー」と「変化」が動画の軸になっています。
また、コロナ禍での仕事環境も少し慣れてきたというか、長い期間をかけて知見や価値観などが熟成されてきたかと思います。少しは明るい未来に向けたテーマになればいいなと思い、コンセプトムービーの雰囲気も工夫しました。
━━全体を通じて、優しい印象です。
そうですね。BGMは尖った音を避けて生楽器を使うなどしてナチュラルな印象を前に出し、生活に溶け込み活かされるテクノロジーというのを見せたかったのでそうしています。
キービジュアルは、今年は多様な色彩でもって表現しようと最初に決めていました。その上で、働き方や考え方の多様性を表現するために、色が混ざりあう部分があって新しい色になったり、それぞれ異なる色が同じ空間の中に存在していることを表現したビジュアルになっています。
━━キービジュアル、動いてますよね?
『いつものやり方+1』につながる話ですけど、キービジュアルは通常はグラフィックデータを作る、描くっていうことになるんですが、今回はまず動画を作ることを前提にし、動画からキービジュアルをつくるという手法で作りました。動画を作って良さそうなフレームを静止画として書き出してキービジュアルにしようと。
なかなかいつもはやらない方法ですね。この他にも水槽に絵の具を垂らしてそれを動画で撮影して作ろうといったアイデアもでました。こうしたアイディアはクリエイティブチームで集まってブレストしたときに出てきたものです。
━━キービジュアルがない状態で、まず動画を作ったと。
正確には、まずはじめに方向性や目指す表現のビジュアルを作りました。それを元に動画を作っています。コンセプトムービーの中でキービジュアルを扱うことは分かっていたので、静止画ではなく動画にしておいた方が、クリエイティブに一貫性が生まれるだろうと。
また、動画は時間という概念のある媒体です。自分たちの考え方や生活も時間によって変化するし、VUCAの時代といった世相を、混ざり合い変化する色や、曖昧な境界と定まることのないカタチとして表現に織り込めると思いました。
━━面白いですね。なんでこういうアイディアが出てきたんですかね。
チャレンジできるだけの時間も多少あったというのもあります、いつものやり方だけじゃなくても良いという前提をおくことで、心理的安全性をやや高める効果もあったのかなと個人的には思っています。
あとはクリエイティブチームを編成したとき、誰がどんなアイディアを出してもいいという環境にしたいと最初に考えていました。サウンドはサウンドに関するアイディアしか出さない。グラフィックは絵だけ、Webはウェブサイトだけ、動画は...…と職能にとらわれないように。
最初、クリエイティブチームを作った時に「こういう感じでやっていこう!」という話はさせてもらいました。
━━最初のマインドセットがすごく効いた?
んー、まぁどこまで効いてたのか分かんないですけど、結果としてそうだったら嬉しいです。あとは僕が色々とはじめてのことも多くて足らない部分もあったので、逆にそれで周りのみんなが自発的に動いてくれたのでは……とも感じています。
全員その道のプロなので、最終的にはなんとかカタチにしてくれるメンバーだとは信じていました。
━━改めて、クリエイティブディレクターとは?
最初は「全てのクリエイティブを統括して、それぞれジャッジしていく」というイメージだったんですけど。もちろんそういう役目もあるし、予算のやりくりなどもありますが、やり始めてすぐに気づいたのは、目的地をどこに設定するか、そしてそこに皆で向かっていける方法を考えたうえで行動できるかということでした。
自分なりの基準を定めて、そこに対して目的やクリエイティブの方向性をしっかり定めて、それぞれのスキルを持った人たちと助け合いながら目的地に到達することだと思います。
余談ですが、めちゃくちゃ雑用もしてました。誰が拾えばわからないようなモノを見つけては、真っ先に拾いにいくみたいな。僕が今回やったことは、一般的なクリエイティブディレクターとは異なるかもしれません。
━━本日はありがとうございました。最後に、学生にメッセージを。
デザイナーやクリエイターって、なにかしら課題があってその問題をちゃんと理解したうえで解決していくっていう仕事なので、つくったものに対して実用性が求められます。
自分がただ表現したいと思う作品を作るのとは少し向き合い方が違ってくると思います。課題を解決するために何かしらの表現でもって具現化し、解決や改善に導く。場合によっては自分で課題を見出すことも求められます。
難しいことでもあるけどやりがいもあるし、その課題解決を自分らしい表現で成し遂げたときには大きな喜びがあると思います。
━━課題の設定から問われる、と。
そうですね。課題の設定というか、真の課題を見つけるというか。仕事の依頼主が課題だと思ってることを咀嚼した上で、自分でも考えて真の課題を炙り出せるとよいですね。依頼主すら当初気づいてなかった真の課題や解決方法を見出していくのも、デザイナーの仕事の一部かなっと思います。
あとは知識や経験が役に立つことは多いので色々経験してみてほしいです。表現というのはアプローチの仕方が無数にありすぎて、どれを選択するかも求められる。そこでは情報、知識、経験も求められることにはなりますね。情報収集の仕方にもそれが活きます。
ミクシィは事業会社なので、0→1もあれば、1→10、10→100、更には100→100という仕事もあります。自分が携わっている事業の課題はなにか、どういう世界を描くべきか。そういうことを考えて、手を動かせる人が活躍すると思います。
